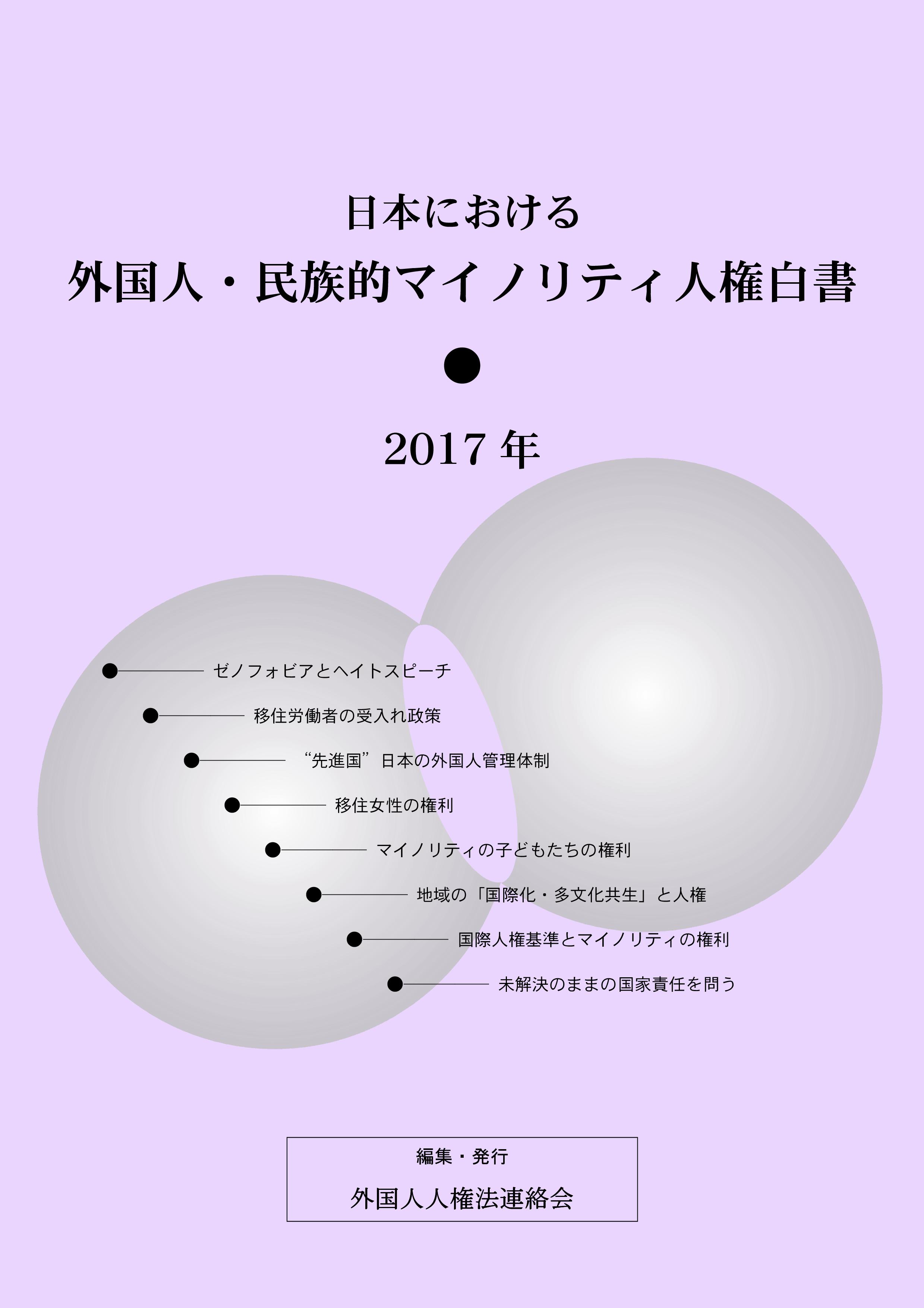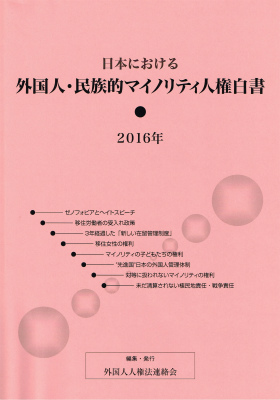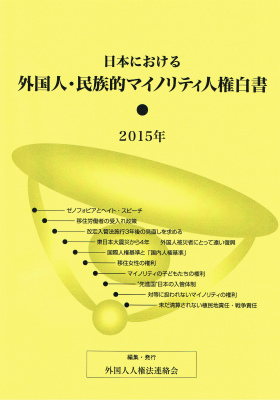外国人人権法連絡会では、毎年「日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」を発刊しています。その2017年版を、2017年3月31日付で発刊しました!
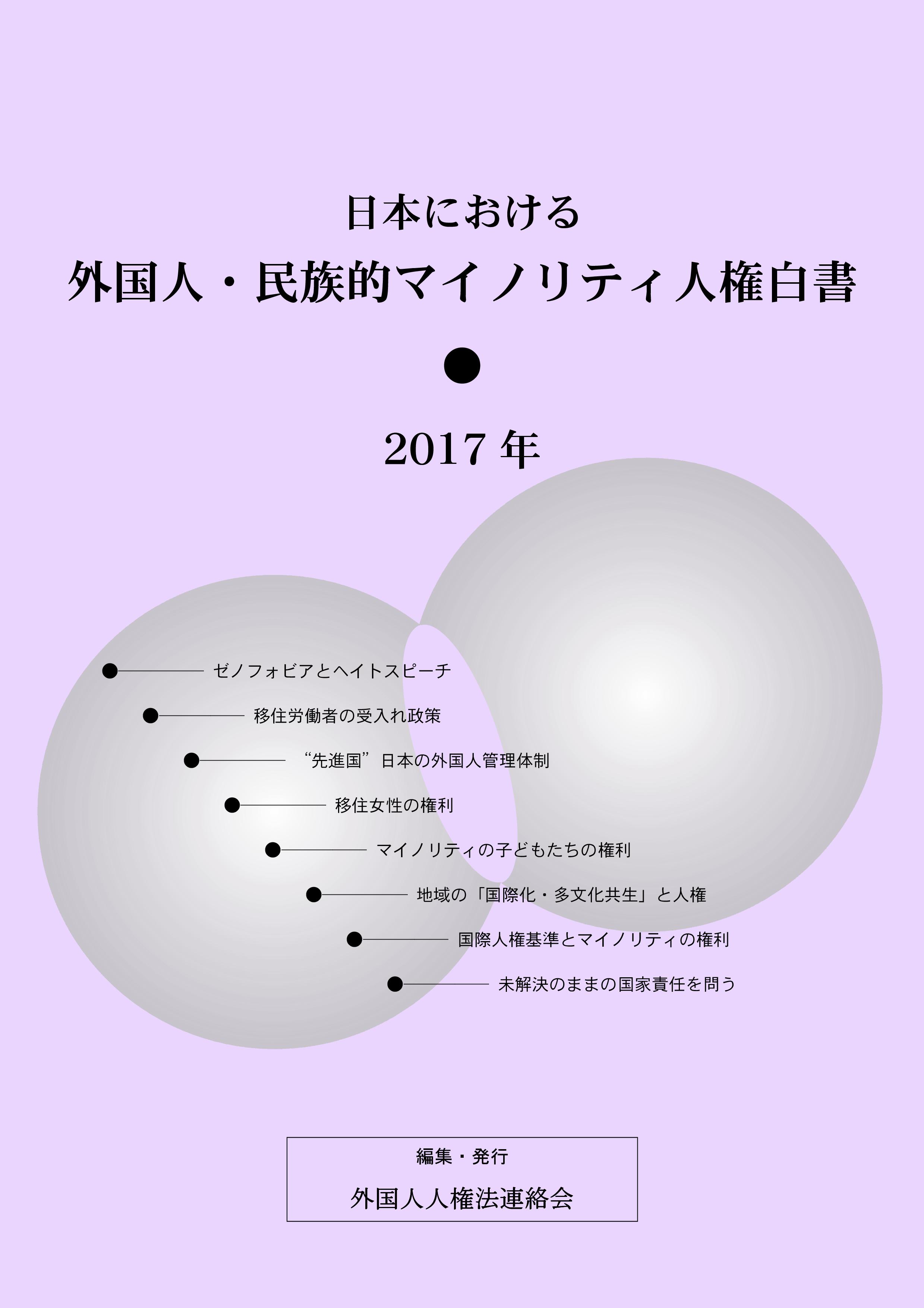
※10冊以上購入の場合は、8掛け
【購入方法】
購入を希望される方は、下記の連絡先まで、
①お名前(個人または団体名)
②送付先住所(郵便番号も含めて)
③電話番号
④e-mail
⑤希望冊数
を、お伝えください。お申し込み後、「人権白書」と郵便振替用紙を送ります。本が届いたら、郵便局で本代を振り込んでください。
【目次】
はじめに ~点描:憲法施行70年と「外国人の権利」
第1章●ゼノフォビアとヘイトスピーチ
1.ヘイトスピーチ解消法の成立
2.解消法成立後の政府の取り組み
3.川崎のヘイトスピーチ根絶運動
4.ヘイトスピーチ規制自治体条例
5.解消法とインターネット対策
6.選挙活動とヘイトスピーチ
7.李信恵さんヘイト裁判地裁判決
8.福岡差別張り紙刑事事件判決
9.沖縄高江での警察官の差別暴言
10.徳島県教組襲撃事件高裁判決
11.震災後の「外国人犯罪」の流言
第2章●移住労働者の受入れ政策
1.拡大する外国人技能実習制度
2.外国人介護労働者の受入れ拡大
3.「外国人家事支援人材」の労働権
4.外国人建設就労者受入事業
5.「強制帰国」に関する不当な判決
6.ベトナムからの技能実習生
7.相談事例に見るビルマ人実習生
8.技能実習生を支えるシェルター事情
9.日系人労働者の制度変更のはざま
10.「留学生」という名の労働力
第3章●“先進国”日本の外国人管理体制
1.日本の難民保護2016年
2.繰り返されるチャーター機強制送還
3.見直されない「新在留管理制度」
4.拡大し続ける在留資格取消し制度
5.「朝鮮」表示者への「誓約書」強要
6.入国審査における新たなテロ対策
第4章●移住女性の権利
1.JFC母子の人身取引
2.移住女性と在留資格
3.DV被害者と在留資格
4.シングルマザーとして生きる
5.勝手に離婚されてしまう協議離婚
第5章●マイノリティの子どもたちの権利
1.外国人生徒の進学問題
2.にほんご×こどもプロジェクト
3.「家族滞在」の高校生の進路問題
4.6年に及んだ桐生いじめ裁判
5.子どもの退去強制処分取消訴訟
6.朝鮮高校無償化除外、補助金停止
7.外国人学校の現況と二極化
第6章●地域の「多文化共生」と人権
1.自治体の多文化共生推進施策
2.外国人集住都市会議の推移と現状
3.非正規滞在者への行政サービス
4.熊本地震時の外国人被災者
5.震災7年目「ふくしま」の移住女性
第7章●国際人権基準とマイノリティの権利
1.琉球沖縄の要求
2.琉球・沖縄の表現の自由
3.アイヌ民族新法の制定に向けて
4.女性差別撤廃委員会審査とマイノリティ女性
5.マイノリティ特別報告者が見た日本
6.蓮舫議員「国籍問題」その前後左右
第8章●未解決のままの国家責任を問う
1.破綻した日韓合意
2.吉見義明氏名誉毀損裁判
3.元BC級戦犯者の立法運動
4.中国人強制連行国賠裁判
5.強制労働問題の現在
6.ビザ発給拒否・集会妨害国賠訴訟
7.「植民地歴史博物館」建設に向けて
8.無年金外国籍障害者・高齢者の運動
おわりに ~人種差別撤廃法の制定を求める
資料1.在日外国人の人口動態
資料2.ヘイトスピーチ解消法・国会決議
資料3.外国人人権法連絡会声明
資料4.移住連声明
資料5.共同通信社 外国人住民に関する全国自治体アンケート
『人権白書』バックナンバー目次一覧
「外国人人権法連絡会」とは